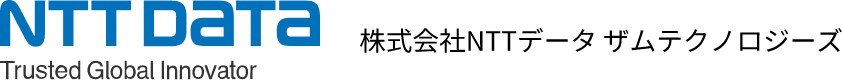生産性の向上
大量生産と対極にあるのが初期のAMの概念だったと認識していますが、現在ではAMでしかつくれない高機能部品を大量に生産できないか?というところが大きな関心ごとになっているのではないかと思います。
ポリマーの造形では例えば100万個ほどのダイオードレーザーを搭載する3Dプリンター(LaserProFusion)が開発されており、量産用に射出成型機の代わりに3Dプリンターが選ばれる日もそう遠い先の話ではないかと思います。
一方、金属造形はそう簡単に生産能力を引き上げることはできないのですが、以下に生産性向上に向けたアプローチを紹介したいと思います。
(1)レーザーのマルチ化
複数のレーザーを搭載することによって造形時間の短縮を図るものです。大型部品への対応も可能となります。しかし、一つの部品を複数のレーザーで分担して造形する場合、レーザーが照射される領域同士の境界部分での結晶構造が他の部分と異なる場合が多々あり、物性の均一性が損なわれる恐れがあります。したがって、レーザーの境界部も含めて均一な機械特性が得られるように十分吟味されたパラメーターを設定する必要があります。またレーザービームのドリフトは避けられない問題なので、レーザー境界部での精度が確保されるように複数のレーザーが常にキャリブレートされた状態を維持されるような仕組みも必要となります。
複数の部品を同時に造形する場合は、どのレーザーがどの部品を照射するかといった最適化も造形時間の短縮化に貢献します。
(2)積層厚の増加に対するパラメータや材料の開発
例えば積層厚さを0.2mmから0.4mmと倍にすると、造形時間はほぼ半分になります。大きな積層厚さでも機械特性、密度などが問題なく造形できるようなパラメータが開発されたり、材料のチューニングが行われています。また精度維持と時間短縮の両立のために、一つのジョブの途中で積層厚を変えることも可能となっています。今後、部品形状を解析し、一つのジョブの中で自動的に積層厚の増減が行われる制御ソフトが開発されると思われます。
(3)プリントドメイン
部品をAMで量産する場合、多くの場合複数の造形機を稼働させることになります。通常造形作業は以下の手順を踏みます。
①段取り :データ準備、材料のセット、造形プラットフォームの調整
②造形 :無人運転
③取り出し :未焼結材料の除去、部品の取り出し
④材料再生 :未焼結材料の回収、シーブ
最近の造形機はそれぞれの作業をクリーンな雰囲気で、あるいは自動的にできるようなユニット構造を採用しているものが多くなっています。EOSはこれらのユニットを単独で機能するモジュールとし、量産に必要な台数の造形モジュール(②)と必要最低数のその他のモジュール(①③あるいは④)で構成するプリントドメインでの運用が可能となっています。
(4)サポート造形の最適化
造形時間のうちでサポート部の造形が占める時間は小さくはありません。この点に関して、サポート形状の最適化によるサポート容積の縮小と、サポート部のレーザー照射ストラテジーの最適化による照射時間の低減の両面で改善が図られています。これによりサポート除去に要する工数も削減されるので、量産性の向上と製造コスト低減、更に品質向上への効果は大きいです。
レーザーの出力を、例えば400Wから800Wに倍増してレーザーの走査速度を倍にすれば、造形時間を半減できるのではないか?ということがすぐ思いつきますが、そう簡単にはいかないところが金属造形の難しいところです。
材料にもよりますが、倍のレーザーパワーを投入したとたん造形できなくなるというのが常ではないでしょうか。
生産性の向上は製造コストの低減、AMの発展に大きく寄与するのでメーカーも全力で取り組んでいます。今後もいろんなアイデアが実現されるのではないかと期待するところです。
著者紹介

略歴
1952年 大阪生まれ
1977年 大阪府立大学大学院工学研究科船舶工学 修士課程修了
1978年 日立造船情報システム(株)入社
1991年 海外事業部部長
1993年 独EOS社と積層造形装置の日本国内における独占販売契約締結。
以後、EOS社の積層造形装置の事業推進に従事し、現在に至る。
2021年 2月1日現在
(株)NTTデータ ザムテクノロジーズ ソリューション統括部 技術部